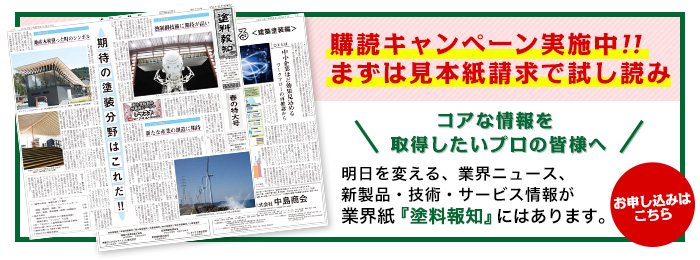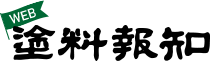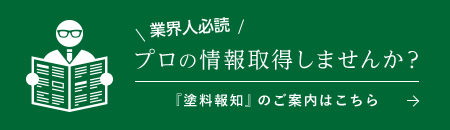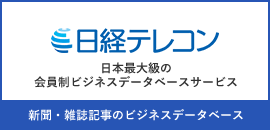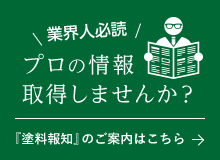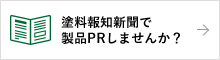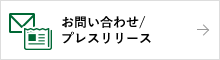NEDO、化学物質の連携実証を開始 化学物質情報をプラットフォーム化
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)は、「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」を本格的に開始した。実施予定先は6月30日に発表済みであり、化学物質情報の流通に関わるシステム開発事業を2027年度に実装する構えだ。
ウラノス・エコシステムとは、経済産業省が推進する企業や業界の枠、国境を越えた横断的なデータ連携基盤の構築を目指す活動の総称である。産業のサプライチェーンは国境を越えて広がり、製品の安全性を確認するためには、川上から川下産業全体での製品に関するデータの流通・共有が不可欠となってきている。こうした中、経済産業省では、異なる組織・国、異業種間において、信頼性を確保したデータ共有の仕組みづくりを目指している。
この基盤の構築が喫緊に求められているのが、蓄電池と化学物質分野である。両分野では輸出時に製品情報の提出が求められる場合があり、サプライチェーン全体での情報共有が必要とされている。蓄電池分野ではカーボンフットプリントの提示等、化学物質(化学物質を使用した製品を含む)では、輸出先地域の規制リストへの適合状況など、安全情報の共有が不可欠である。近年の欧州における資源循環や化学物質情報管理の強化といった動きに対応することが急務となっている。特に化学物質に関連する企業は約1万社に上るとされ、流通に関わるシステムは大規模なものになることが予想されている。
これに対し、具体的な仕組みとして、製品含有化学物質情報と併せて部品リユース情報やリサイクル材情報までを伝達可能とする「製品含有化学物質情報・資源循環プラットフォーム構想」(Chemical and Circular Management Platform、以下CMP)が立ち上げられている。CMPは、川上から川下までの動脈系企業(資源をもとに製品を設計・製造し、流通・販売までの領域の産業)などが化学物質情報に容易にアクセスできる総合的な情報伝達基盤であり、生産性の向上も期待されている。欧州では同様のシステムがすでに実装されており、導入が進む同情報基盤にも対応可能な方向で進められている。
データ連携システム構築・実証事業は2025年度から2027年度までの実施を予定しており、2025年度の予算は16億4900万円。事業では9件のテーマが採択され、そのうち6件が化学物質情報の流通に関わるシステム開発事業である。NTTデータが化学物質情報のトレーサビリティ管理システムを開発し、アプリケーションの開発・実証をdotD、Sotas、日本電気、富士通がそれぞれ担当する。また、資源循環の静脈系における化学物質情報のトレーサビリティ管理に関する調査・研究は野村総合研究所が担当する。
各アプリにはそれぞれの特長があり、たとえばSotasでは、化学物質管理アプリ「Sotas化学調査」の既存サービスに「CMP連携機能」を追加し、既存ユーザーからのフィードバックを得ることで、主にサプライチェーンの川上側の企業へのCMP普及に貢献し、ウラノス・エコシステムの実現を目指している。