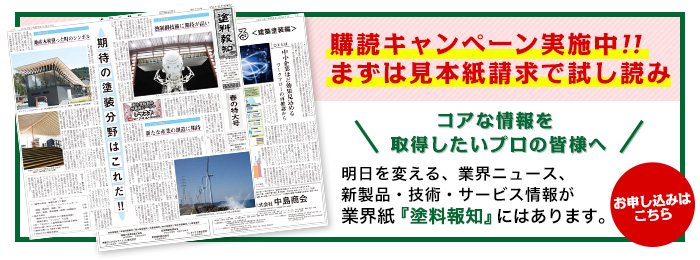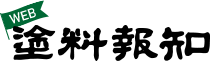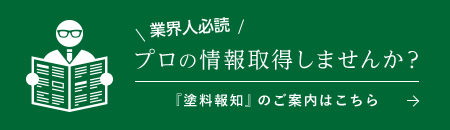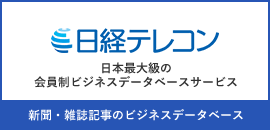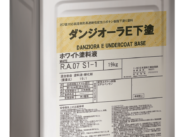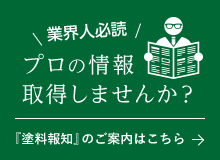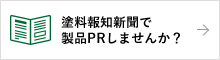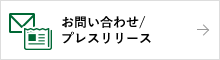日本塗り替え研究会、対話型フォーラム
日本塗り替え研究会は、次世代の塗料・塗装事業経営者を対象に「塗装フォーラム2025~変革の先にある未来~」を8月19日午後1時30分から東京都渋谷区恵比寿の東京塗料会館で開いた。

対話型フォーラムに参加した一同
建築塗料業界を取り巻く環境が大きく変化するなか、現場の最前線で活躍する塗装事業者を中心に〝これからの住宅塗り替え業界〟を語り合った。後援は塗料報知新聞社事業局。
【第1部】は「日本を塗り替える」を奥村政佳氏(元参議院議員)、「建築塗料市場の最新動向」を津村昌伸氏(日本塗料工業会調査部長)から講演があった。【第2部】のパネルディスカッション1は「現場のリアルと展望~現場の声から見えてくる、住宅塗り替え業界の今と未来」と題して、〈パネリスト(塗り研会員)=内山雅彦氏(会長・内山建装/静岡)、斉藤大信氏(副会長・hinata/奈良)、宮崎克己氏(前会長・江本塗装/愛知)、佐々木将行氏(ユニマックスペイントシステム/岐阜)、司会=田中茂氏(副会長・ペン・テック/岐阜)〉が、また【第3部】のパネルディスカッション2は「業界の知見と未来へのヒント~塗装業界の立ち位置を多角的な深掘りで見直す」と題して、〈パネリスト=第1部の奥村氏や第2部パネリストに加え、工藤一秋氏(日本塗装技術協会会長/東京大学生産技術研究所教授)、國島久嗣氏(クニシマ社長/日本塗料商業組合元副理事長)、有馬弘純氏(塗料報知新聞社社長)、司会=田中茂氏〉が討論した。
参加者からは次のような声があった。
経営者の考え方にそれぞれ違いはあれど、皆さん情熱的で信念をもって経営されていると感銘を受けた。特に、創業100年を超える國島氏の「先の事は結局わからない」という言葉が印象的だった。常に変化を続けていけるか、成長していけるか、が強い会社を作る方法なのかなと改めて感じる良い機会となった。
また、業界の現状や今後の方向性、課題、次世代に向けた取組みなど、非常に有意義なディスカッションが繰り広げられた。津村氏の講演では塗料の市場シェアや成分の構成比など、業界全体のリアルな動きが明らかにされ、「より良い塗装をお客様に届けるために、今できること」を改めて考える機会になった。
塗装業界もどんどん変わっていく。そして、変えていかなければいけないと、改めて気付かされた。ただ塗るだけじゃない。お客様の笑顔のために、建物の未来を守るために、業界としての責任と使命を持って進化していく必要があると感じた。これからも現場で汗をかきながら、地元の皆さまの住まいを守るため、進化した塗装で現場に活かしていきたい。各方面の専門の方から、いろいろな話が聞け、とても楽しく、勉強になった。新しい気付きもあった。ありがとうございます。
会場では、現場感とアカデミック感のハーモニーが良く、「これを塗ったら一生塗らなくてもいい塗料って、この先、開発されますか」に対して工藤先生が答えるシーンや、他業界を引き合いに、保育士を斡旋する会社による高額な手数料が現実となるなか、自分達の業界は自分達で守っていかなければならないとの奥村氏による発言は印象深かった。3時間半に及ぶ全体を通し、昨今のWEB開催、質疑応答もメール送信の形式が増えるなか、対面開催ならではの熱量が伝わってくる場であると感じられ、参加者全員から熱心さが伝わる非常に充実したフォーラムであった。また、話題に上がったクレーム対応の難しさなども非常に興味深い内容が詰まっていた。
今回、同研究会において、「目先の仕事を回すことに囚われていると異業種に利益を吸い取られ、気付いたらジリ貧になってしまうということも十分に考えられる。だからこそ、塗る作業が人の暮らしを守り、まちを彩り、仕事を通して仲間や家族の人生を支えており、自分達の業界は自分達で守っていかなければいけない」といった良い気付きを得られたようだ。終了後、浜松町へと移動し、東京湾クルーズを楽しんだ。