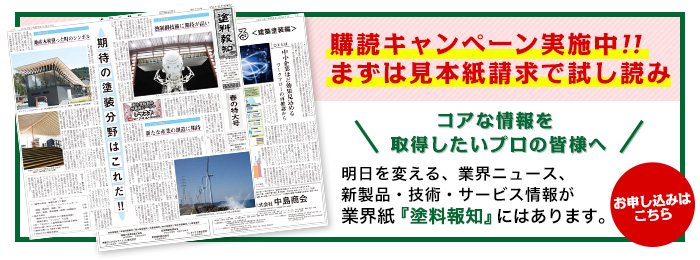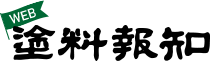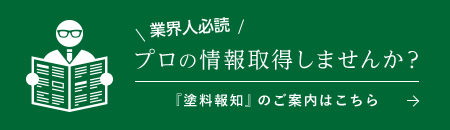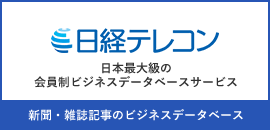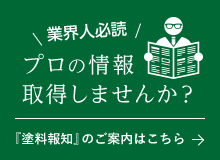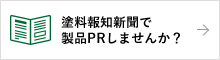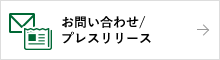【インタビュー】大阪・関西万博催事検討会議共同座長・大﨑洋氏
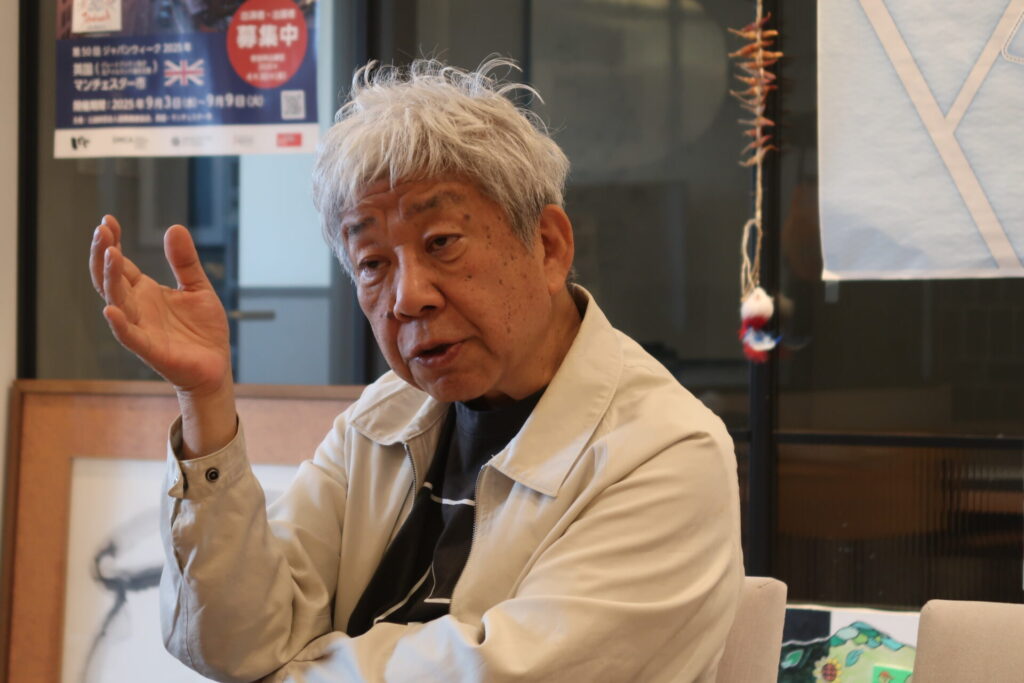
大﨑 洋氏(おおさき・ひろし)1978年吉本興業(現・吉本興業ホールディングス)に入社。09年代表取締役社長に就任。19年代表取締役会長。23年6月取締役を退任。同月一般社団法人mother ha.haを設立し、代表理事に就任。沖縄国際映画祭実行委員会委員長、京都国際映画祭実行委員会委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局わくわく地方生活実現会議委員、内閣府基地跡地の未来に関する懇談会委員、内閣府知的財産戦略本部構想委員会コンテンツ小委員会委員、鳥取大学医学部附属病院運営諮問会議委員、近畿大学客員教授、公益財団法人国際親善協会クリエイティブディレクターなど歴任。
万博開幕―注目点と期待される開催効果
観光経済新聞、東京交通新聞、塗料報知、農村ニュース、ハウジング・トリビューンの専門5紙誌は2025年度の連携企画第1弾として、4月13日に開幕した「大阪・関西万博」をテーマに取り上げた。「大阪・関西万博催事検討会議共同座長」を務める大﨑洋氏(mother ha.ha代表理事、吉本興業前社長)に「大阪・関西万博開幕―注目点と開催効果について」をテーマにインタビューした。
―大阪・関西万博が開幕。今の心境を。
多くの方が数年かけて開催に向けて準備を進めてきた。いろいろと叩かれて、ミャクミャクだけが人気だが(笑い)、来場した人から「すごく良かった」という話をたくさんいただいており、今はうれしく、ほっとしているところだ。名称は「大阪・関西万博」だが、実際は国全体の祭典だ。全国津々浦々、さまざまな地域の魅力を紹介する。各都道府県の風景や産品を展示したり、イベントを行ったりする。会場には世界各国のパビリオンもある。会場にいながらにして日本各地や海外への旅行ができる。国内各地の伝統芸能や工芸、世界のさまざまな祭りや風習を見て、体験してもらえる。特に子供たちにとって良い機会だ。先日、4日間続けて会場に行ったが、小・中・高校生がたくさんいて、みんなパワフルに会場を回っていた。天気も良く、多くの人が大屋根リングに上っていた。リングの上からは、和歌山、淡路島、神戸の方の街や海、大阪市内、奈良の方の山々まで一望できる。みんな「わーっ」と子供からお年寄りまで歓声を上げていた。
―会場に行った人から、大屋根リングは一見の価値があるし、場内がとにかく広いとの感想を聞いた。
実は、前回の1970年万博の方が会場は広かったのだが、今回の万博もかなり広いことは間違いなく、とても1日では回り切れない。だから何度でも行ってもらいたい。私も今度、親戚にも声をかけて、家族みんなで行こうと思っている。普段、なかなか会えない人もいるのだが、会うためのいい機会だと思い、誘うつもりだ。
―大﨑さん自身が開幕までに、特に尽力されたことは。
開幕式をどうするか、同じ共同座長(大阪・関西万博催事検討会議共同座長)の池坊専好さんといろいろ話をした。限られた予算の中でどうするかが大きなテーマだった。会期中は地方のさまざまなイベントを3千件ほど行うのだが、それに対する万博協会からの予算はゼロだ。国際規定で決まっているというのだが、約3千のイベントを予算ゼロで行うと聞いて、参ったなと思った。そこでお祭りをキーワードにしようと思い、各地方の方々から協力をいただいた。祭りには日本人の美意識がいっぱい詰まっている。みこしを担いだり、太鼓を叩いたり、周りには屋台があって地産地消の食べ物を食べたりと、老若男女、みんなが楽しめる。海外の人たちには、日本の本当の素晴らしさを肌で感じて、次に来日するきっかけにしてもらえるだろう。「次は群馬県に行こう」「佐渡島に行こう」「種子島に行こう」と、日本各地に行ってもらえるようになればうれしい。
今回の万博のテーマの一つといえば、さまざまな社会課題の解決だ。前回の70年万博は、「敗戦から立ち直り、先進国の仲間入りをした日本はこんなに立派になりました」「世界中の皆さん、どうぞお越しください」とアピールしていた。世界の国からこんにちは」と、三波春夫さんが明るく高らかに歌っていたが、実はあの歌は16人ぐらいの歌手が歌い、全てのレコード会社から発売されたという。国を挙げて「万博万歳」という風潮で、初期の頃は今と同じようにマスコミに叩かれまくっていたそうだが(笑い)、国を挙げて祭りを行っているような状況だった。
それに対して今回の万博のテーマは、少子高齢化、自然災害など、日本が抱えているさまざまな課題の解決。世界の英知を集めて、これらを少しでも解決していきたい。振り返って、課題解決のスタートとなった万博だったといわれるようにしたい。社会課題の解決というと、つらく厳しいイメージがあるので、お祭りのように楽しくやろうと今、行っているところだ。最近、ある地域の太鼓祭りの関係者とお会いした際、「祭りを世界デビューさせたい」「祭りを継承する地元の若者たちに夢を持たせたいが、何かアイデアはないか」と相談をいただいた。わが町、わが村の伝統文化や産品を世界デビューさせたいという意識が、万博の開催を契機に、各地でかなり高まっていると感じる。
日本は国全体が万博会場
―前回の70年大阪万博当時の思い出や、印象に残っていることは。
私は高校生だったが、当時の日本人は外国の人を生で見ることがあまりなかった。それが万博会場に行くとたくさんいるわけだ。「金髪の人は本当に髪が金色なんや」とか(笑い)。動く歩道や、人間洗濯機みたいなものもあって、「自分の体ぐらい自分で洗えよ」と突っ込んだり(笑い)。でも、先日、足が痛くなって入院したのだが、駅に着くと真っ先に動く歩道を探したり、病院でお風呂に入れてもらったり。半世紀前に万博で見たものに、71歳になった今、お世話になっている。今思えば当時の万博はまさにテーマである「人類の進歩と調和」だった。
東京の人に話を聞くと、当時の大阪は今のように多くのホテルや旅館がなく、多くの人が親戚や知り合いの家に泊まっていたという。それが今はホテルだらけで(笑い)、特に大阪の南、難波から西成にかけて、宿泊客の8割はオーバーかもしれないが、それぐらいがインバウンドという印象だ。今回の万博を契機に、大阪の街はさらに変わるのではないか。海外から注目され、人の流れがさらに活発になる。観光業に関わる人にとっても、うれしいことがたくさん起きるのではないか。大阪に限らず、日本の各地を旅行したり、場合によっては移住をするという流れが起きるかもしれない。
インバウンドの方から見れば、日本全国が万博会場のようなものだ。和食を食べて、温泉に入り、畳に布団を敷いて寝る旅館などは目新しく、体験して心がワクワクするだろう。外に行けば銭湯がある。私は銭湯が大好きなのだが、そのような庶民が行くところにもぜひ行ってもらいたい。地域住民、特に子供たちにとっても外国人との交流が図れる絶好のチャンスとなる。インターナショナルスクールにただで通うようなものだ。オーバーツーリズムなどの弊害があるものの、今回の万博をうまく日本全体の成長に生かしていければいい。
―今回の万博で注目すべき展示やイベントをさらに挙げると。
個人的にすごいと思ったのが、パソナさんのパビリオンで展示されているⅰPS心臓。培養液の中で、生きているように動く。命の輝きを感じ、感動する。先進医療の普及、実用化へ、お年寄りから子供まで、夢を与えてくれるものだ。近畿5府県と近隣の4県が出展する関西パビリオンもさまざまな展示が行われている。若い、世界的なアーティストとコラボして、地域の工芸品をアートのように展示したり、映像を駆使したりと、各府県が工夫をしており、見どころがいっぱいだ。「恐竜王国」の福井県は恐竜、お伊勢さんの三重県は精神世界、琵琶湖の滋賀県は「私たちの宝のマザーレイク」、それぞれが特徴を生かした展示をしている。各自治体とも相当な準備と工夫をして、自分たちの宝を表現している。 ほかのパビリオンやイベントも、それぞれ必ず見どころがある。
―今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。
各パビリオンとも、当然、テーマに基づいた展示やイベントを行っている。さまざまな表現の仕方をしており、観客がどう感じるかは人それぞれだが、テーマに沿った形で行っていることは間違いない。
―展示された最先端技術が数十年後には実用化されているのだろう。
さまざまな技術が進化しており、チャットGTPなどもこの1カ月ですごく進化している。「そんな格式ばった言葉じゃなくて、大阪弁でしゃべって」と言うと、「ごめん、ごめん、ほんまにそうやなあ。うち、これから大阪弁でしゃべるわ」と(笑い)。
―未来の交通、特にバス・タクシーについて、思い描くものは。
環境に優しい、持続可能というところがキーワードになるだろう。EVバスが万博会場で実用化され、既にそれほど未来を感じるものでもないが、地方でも普及が進めば「万博の乗り物がわが町にも来た」と喜ばれるだろう。外国では無人のタクシーも実用化されている。ただ、その分、人と人との触れ合いがなくなってしまう。コミュニケーションの部分をどう補うかを考えなければならない。空飛ぶクルマも、日本は規制が厳しく世界から遅れている部分もあるが、その分、安心安全が担保された上で実用化されるだろう。科学の進歩は大事だが、進歩をちょっと止めて、休むことも必要かもしれない。新しい技術は包丁と一緒で、使い方を間違えれば人を傷つけたり大変なことになる。慎重な対応が必要だ。
―今回の万博が日本社会にもたらす影響について。
一つの場所に老いも若きも集まって共通体験をする。孤立、分断、格差の拡大、中間層が減ったなどといわれる中で、これはすごく大事なことだ。今の時代、3世代が一緒に暮らすことはあまりなくなっているが、何かを契機にみんなが集まり、世代によって異なる悩みや不安を自分事として考える。万博がそんな良いきっかけになればいい。
地域の〝宝〟知る機会に
―専門紙・誌を購読する読者へ、最後に一言。
日本はさまざまな宝が詰まった宝箱であり、国全体が万博会場のようなものだ。万博を機に海外の方に来てもらうことによって、自分たちが今まで気づかなかった地域の宝、さまざまな魅力を知ることになるだろう。何かの本で読んだが、海外の方が地方の旅館に泊まってよく質問するフレーズが「イズ・ディズ・ローカル・ミール?」。要は、「私たちはパンやスープやハムエッグを食べに来たのではなく、あなたたちの地元に代々伝わる料理を食べに来たのだ」と。高野山のある宿坊にヨーロッパの方が1カ月などの長期滞在をするという。精進料理を毎日出すのだが、「たまにはパンとコーヒーを」と言うと、怒られるそうだ。
地域に伝わる何気ないもの。これらが実は、地域の宝物なのだ。万博はそれに気づかせてもらえる大きなチャンスだ。新たな気づき、ビジネスチャンスが大中小を問わず、生まれてくるはずだ。地方創生に、都会のシンクタンクや広告代理店が関わることがある。間違っているとは言わないが、地域の人たちが自主的に「自分たちが本当に大事にしなければならないものは何だろう」と考えることも必要なのではないか。