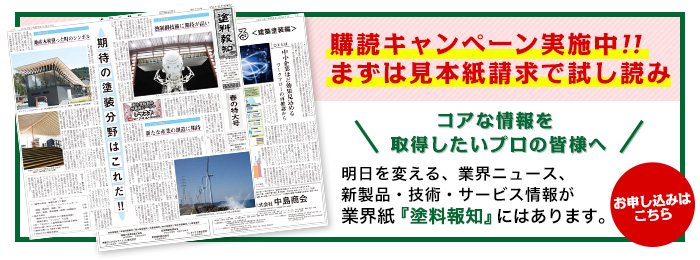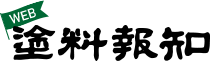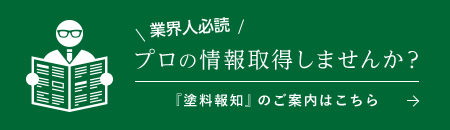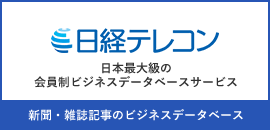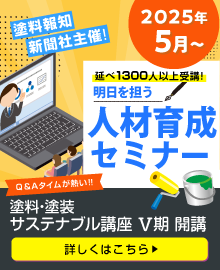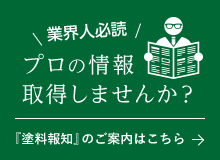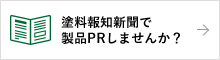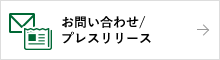塗料塗装普及委、建築塗料・塗装セミナー
日本塗料工業会(若月雄一郎会長)、日本塗料商業組合(中山保幸理事長)、日本塗装工業会(加藤憲利会長)からなる塗料塗装普及委員会は「2024年度 建築塗料・塗装セミナー」を2月6日午後1時15分から、東京塗料会館とWEB配信で同時に開催。また、21日までオンデマンドで配信した。

会場にて業界の現状を伺う聴講者
日塗工の児島與志夫専務理事による開会のあいさつに続き、「建築塗料のトピックス」と題し、第1部は建築塗料市場の最新動向を日塗工技術委員会・建築塗料部会委員の津村昌伸氏、第2部は低VOC塗膜性能調査のまとめを東京都環境局環境改善部化学物質対策課揮発性有機化合物対策担当の荒井来途氏が発表した。
第1部で津村氏は、日本の新設住宅着工数の推移では、2021年度は前年度比7・0%増もその後、現在までの回復は低調であるとの見通しである。塗料全体の生産・出荷量は、2023年の生産量は前年度比0・6%減の147万トン、出荷量は同1・7%減の153万トンとともに減少したが、出荷金額のみが同5・8%増の7381億円という結果であった。金額のみが上回った要因としては、原材料や輸入価格の高騰による各社の値上げが考えられる。需要産業別出荷数量では、建物用塗料が全体の約24・7%を占めており、出荷数量は32万トン。そのうち水系塗料のエマルションペイント32・7%、圧膜形エマルション32・6%と合わせて65%を占めており、水系化が進んでいる。建築用塗料の内装用では、JIS K 5663の合成樹脂エマルションペイント(EP)の出荷数量においては、建築用全体の5~6%ではあるが2021年以降増加の傾向であったと述べた。
第2部では荒井氏が、東京都の2010~2020年までのVOCの調査結果について解説。 この10年間環境基準を設定し対策を行い、ほとんどの項目で大きく改善した。しかし、光化学オキシダントの環境基準が達成できていない。VOCやノックスが原因で光化学スモッグが発生、2023年は4回であったが、2024年は15回と多発。塗料・塗装業界においても2000年からの20年間でVOCは半分以下に減っているが、排出割合では全体の4分の1を占めている。今後、屋外塗装、工場内塗装へのさらなる対策や支援が必要であるとした。東京都では低VOC塗料で塗装されたパネルを屋外に設置し、低VOC塗料開発や普及啓発促進を目的に、経年変化の塗膜性能調査を行っている。調査方法から結果を公表し、説明した。
続いて「海外を通して見えた日本の建築人材確保・育成の未来」と題し、第1部は、ドイツ・ベルギーにおける建設人材の処遇と育成制度について、日塗装常任理事兼技術委員長の伊藤龍平氏、第2部は、技能実習・特定技能による外国人材の受入れ~インドネシア視察や自社の状況を踏まえて~を、同会副会長の若宮昇平氏が発表。
第1部で伊藤氏は、昨年10月海外視察の体験を基にドイツとベルギーの建設人材の育成制度について発表。ドイツでは、視察①マンハイム教育センターで、3年間のトレーニング終了後、資格証明書を発行(高卒資格含)、終了により給料がほぼ倍になる等の優位性、視察②SOKA―BAU(ドイツの社会保険関連団体)では、労働者の処遇改善、労働者の技能研鑽、建設工事の受発注方式について、ベルギーに移り、視察③EU(DG-GROW・欧州委員会成長総会)は日本の省庁に相当し建設産業政策に関与、非EUの外国人労働者数のコントロールと処遇の確保、EU内資格の相互承認について、視察④FIEC(欧州建設業協会)ではEU加盟国と国ごとでやることを分けている、2種類の法律があることなどを説明した。欧州は、建設職人の賃金は日本に比べ高いと思われるが、物価も日本の2~3倍程度。GDPは上がるため国力も上がるのでは、とまとめた。
第2部では若宮氏が、若宮塗装工業所を紹介。2023年から、外国人技能実習生の受入れを検討。特定技能と技能実習を比較し、技能実習は1年目から実技と学科試験が必須。合格後2~3年目は技能実習2号となる経緯と、同社におけるミャンマー技能実習生の受入れ事例を、スライドと動画を用いて説明。同社では、25人中2人が採用となった。特定技能については、ルート1は技能検定3級、日本語能力N4レベルが必要。ルート2は技能実習2号が終了すると移行が可能となっており、現状はこちらが主流である。日塗装はJAC加盟団体のため会員企業の加入不要のメリットを解説。日塗装会員の特定技能1号は現在、99社183人(2024年12月末時点)。現行の技能実習が育成就労制度に見直しとなる概要も説明。同会の新たな取組みとして、ルート1の受入れ活動の一貫としてインドネシア合同説明会に参画。全3回の開催と、説明会の様子をスライドで公開。塗装分野での人材育成と受入れの道筋を作ることが重要であるとした。